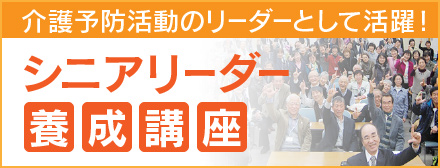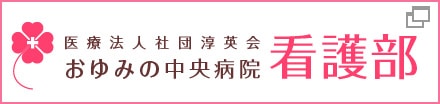変形性膝関節症
人工膝関節全置換術(Total Knee Arthroplasty, TKA)
傷んだ膝関節全体の骨、軟骨を切除して、大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)それぞれの表面に金属でできた人工関節を被せることで関節の痛みをとり、機能を再建する手術です。余分な骨を切ると同時にすり減ってしまった分を補うことでO脚やX脚を矯正します。筋肉への損傷は最小限としており、手術翌日から歩行訓練を開始します。
人工膝関節単顆置換術(Unicompartmental Knee Arthroplasty, UKA)
膝関節の傷んでいる部分(おもに内側)だけを切除し、金属でできた人工関節を被せることで関節の痛みをとり、機能を再建する手術です。
骨の変形が比較的軽く、大腿骨と脛骨をつなぐ靱帯に問題がない方で、膝の曲げ伸ばしが良好な場合に適した手術です。O脚やX脚を矯正することはあまりできません。
人工関節全置換術(TKA)に比べて皮膚の切開が小さく、骨の切除や筋肉への損傷が少ないため、術後の回復が早くなります。

膝周囲骨切り術(Osteotomy Around the Knee, AKO)
膝関節の軟骨や骨が傷むことで曲がってしまった脚を、骨を切ってまっすぐに矯正し、金属の板(プレート)とネジ(スクリュー)で固定する手術を骨切り術と言い、脛骨近位骨切り術(High Tibial Osteotomy, HTO、Distal Tuberosity Osteotomy, DTO)、大腿骨遠位骨切り術(Distal Femoral Osteotomy, DFO)といった術式があります。
多くの変形性膝関節症では膝の内側から変形が進行し、徐々にO脚になっていくため膝の内側にさらに負担がかかり痛みの原因となります。脚をまっすぐにすることで、内側にかかる体重の負担を軽減することで痛みとれることが期待できます。
60代以下の比較的若い方でスポーツなどの高い活動性を希望される方に適した手術ですが、ご高齢の方でも骨が丈夫で体力がある方では適応となることがあります。

病気の原因
変形性膝関節症
膝関節の軟骨の摩耗や骨の変形に伴って痛みや曲げ伸ばしの制限が生じ、歩行などの日常生活動作に障害をきたします。
原因としては、加齢、体重、外傷などが主たるものです。

関節リウマチ
関節を包む滑膜という組織が自己免疫反応によって異常増殖することによって関節内に慢性の炎症を生じる疾患で、進行すると関節が破壊され様々な程度の機能障害を引き起こします。
関節症状に加えて貧血や微熱、全身倦怠感などの全身症状を合併することもあります。
特発性膝骨壊死
膝関節の骨の一部に壊死が生じる疾患です。大腿骨内側顆(太ももの内側で体重を受ける場所)によく起こることが知られています。原因不明の疾患ですが、近年では膝の重要なクッションの役割を果たす半月板の損傷が引き金になることがわかってきました。
変形性膝関節症と比べて、発症が急で強い痛みを生じます。
初期にはレントゲン検査でわからないこともあり、MRI検査が有効です。
3ヶ月程度の安静や痛み止めの治療で症状が改善してくる場合も多くありますが、時間とともに壊死部の陥没が進行し、痛みが増強する場合には手術の適応になります。

膝関節の症状
1.膝関節に痛みが生じる
- 立ったり、座ったり、階段の昇り降りの時に痛みを生じる(第1段階)
- 平らなところを歩いている時にも痛むようになる(第2段階)
- じっとしているときや夜寝ているときにも痛むようになる(第3段階 = 末期症状)
2.膝の動きが悪くなる
曲がらなくなる(正座ができなくなる、和式トイレが困る)
完全に伸びなくなる(膝の後ろが突っ張る)
3.変形をおこす
O脚やX脚になる
治療
いずれの病気でも、まず手術ではなく保存治療を行います。保存治療の基本は体重管理とリハビリでの筋力維持ですが、必要に応じて湿布などの外用薬や痛み止めの内服、関節内注射などを併用します。こうした保存治療を行っても長い年月の経過では徐々に軟骨はすり減って行き、関節の変形は進行します。症状が改善せず、日常生活でこれまでできていた動作に支障をきたすようになった場合に、痛みをとって機能を回復する目的で以下のような手術を検討することになります。
手術方法と適応
人工膝関節全置換術(Total Knee Arthroplasty, TKA)
適応
- 年齢(60歳以上が目安)
- 痛みがひどく、日常の生活に支障をきたしている
- 大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)の間に軟骨がほとんどない
- 骨の変形が進行している
- 膝関節の動きが悪い(まっすぐ伸びない、あまり曲げられないなど)
- 保存治療(体重管理、リハビリ、内服薬、関節内注射など)では痛みが改善されない
など

人工膝関節単顆置換術(Unicompartmental Knee Arthroplasty, UKA)
適応
- 年齢(60歳以上が目安)
- 軟骨や骨のすり減りは内側(または外側)に限定されていて他の部分の軟骨や靱帯の機能が十分に保たれていること
- 膝蓋骨のすり減りはあっても、その痛みが強くないこと
- 関節リウマチのように関節全体に及ぶ炎症性疾患ではないこと
- 高度な肥満ではないこと
- 肉体労働者やスポーツ愛好者の場合は、術後の制限について理解が得られること
など

人工膝関節(TKA・UKA)の比較
| 人工膝関節全置換術(TKA) | 人工膝関節単顆置換術(UKA) | |
|---|---|---|
| メリット |
|
TKAのメリットに加え、さらに体への負担が少ないため、
|
| デメリット |
|
|
| 合併症 |
|
左記に加えて
|
| 手術時間 | 90分~120分 | 70〜90分 |
| 術創 | 12~14cm | 8~10cm |
| 手術後の痛み | TKAは関節全体の骨、靱帯、筋肉などを切除したり剥離したりするため、UKAよりも痛みは強くなります。 | |
| リハビリ | 基本的に変わりないが、UKAで目標達成時期が早い傾向にあります。 | |
| 入院期間 | およそ3週間 ※手術前の筋力・歩行能力によってこれよりも長くかかる場合があります |
およそ2週間 |
| 日常生活に回復するまでの期間 | およそ1-2ヶ月 手術後2週間程度で手術前よりも歩行は楽になります。 |
およそ1ヶ月 手術後1週間程度で手術前よりも歩行は楽になります。 |
| 手術の影響で膝の腫れやむくみは6ヶ月程度かかります | ||
| 術後の生活 | 人との接触が伴うコンタクトスポーツは避ける。正座についてはできる方もいらっしゃいますが、人工関節への負担を考え、お勧めはしていません。 | |
| 耐用年数 | 15~20年で約5〜10%の人に再置換術が必要となる可能性があります | 15~20年で約10〜20%の人に再置換術が必要となる可能性があります |
膝周囲骨切り術(Osteotomy Around the Knee, AKO)
適応
- 年齢(70歳以下が目安)
- 登山やマラソンをしたい、スポーツを楽しみたいなど活動性が高い
- 大腿骨と脛骨をつなぐ靱帯機能が良好で膝の安定性が保たれている
- 変形性膝関節症の進行度が中等度程度
など
メリット
- 人工関節手術と比べて侵襲が少ない
- 関節が温存され、骨が癒合してプレートを抜けば人工物がなくなる
- 手術後の日常生活に対する制限が比較的少なく、スポーツや正座も可能になる例が多い。
- 手術翌日から立つこともでき、1~2週で歩行可能、入院期間は2〜3週間程度
デメリット

リハビリテーション
手術の前日に現在の状態の評価、術後合併症予防の運動や脱臼に注意が必要な姿勢について説明を行います。
手術後以下のようにリハビリテーションを行います。 ほとんどの方が術後3週前後で退院となりますが、必要に応じて、当院の回復期リハビリテーション病棟でリハビリ継続いただきます。
筋力トレーニング
膝を伸ばしたまま足全体を持ち上げる練習や、膝に力を入れて伸ばす練習などがあります。
筋力がないと力が入らず歩けないので、手術翌日から練習を始めます。

関節を動かしやすくする

車いす・歩行練習
手術翌日から車いすに乗車や歩行練習を開始し、まずはトイレでの排泄獲得を目指します。歩行練習は、歩行器から実施し、徐々に杖歩行、独歩と練習をしていきます。
大まかな日程は以下の通りです。
- 手術翌日 歩行器での歩行練習、車椅子乗車
- 1~2週 一本杖を使っての歩行練習
- 約2週半 独歩あるいは杖歩行で退院

生活動作練習
歩行が上手になってくるにつれて階段、床からの立ち上がりなどの自宅で生活するための練習が加わります。
患者様個人の生活に合わせて自宅退院の際に必要な生活動作を練習していきます。

退院後の生活について
できること
- 通常の生活や旅行などは差し支えありません。
- スポーツや車の運転などの再開は医師の指示に従いましょう。
- 膝立てについては、ドスンと着地しない限り、問題ありません。
注意が必要
- 人工膝関節 → 摩耗、ゆるみ、破損など
- 膝周囲骨切り術 → 再骨折、骨切り部の癒合不全など
上記を避けるために
- 膝への負担が大きくならないように体重増に注意する
- 床へのしゃがみ込みなど深く膝を曲げる生活動作を注意する
- 転倒に注意する
高齢者の転倒事故のおよそ半数が自宅で発生しています。
浴室・脱衣所、庭・駐車場、ベッド・布団、玄関・勝手口、階段の順番で転倒事故が多くなっていますので、手すりなど何かに手を添えて安全に移動できるように環境の見直しをお願いします。